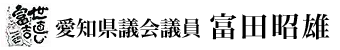令和6年総務企画委員会 2024年12月12日
【富田昭雄委員】
被災地の避難所の環境について、能登半島の被災地においても、いまだ雑魚寝をしている状況が続いていると聞いている。
そのような中で、スフィア基準というものをよく聞くが、このような基準をどう取り入れ、どのようなものを準備していくのか。避難所の環境整備について、日本はまだ遅れていると思う。台湾などは災害が起きた際には物はスピード感をもってベッド等の環境整備が行われていると聞いている。
避難所の収容人数にも限りがあり、地域の人が全員避難することはできないと思うが、どのような人が避難所に避難することを想定しているか。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
自宅の建物が大きな被害を受ける、断水が続いているなどの理由により、自宅で生活することが困難であるという被災者が避難所に避難することを想定している。
なお、市町村ごとの具体的な避難者の数は、愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査報告書で示している。また、各避難所の収容人数については、各市町村が地域防災計画で示している。
【富田昭雄委員】
答弁自体はそのとおりであると思うが、いざとなるとうまくいかないこともあるため、防災訓練等、地域としっかり連携をとる必要があると思う。
その上で、避難が必要な被災者に、避難の呼びかけを行うことが必要だが、どのような方法で伝達するのか。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
市町村において、防災行政無線や緊急速報メール、SNSなどを用いて住民等へ情報を伝達し、避難を呼びかけている。
市町村では様々な場所に居住、滞在している住民や観光客等に対して、避難の指示や避難所開設の情報が早急、確実に伝わるよう、伝達手段の多重化、多様化を図っている。
県としても、愛知県防災ウェブを開設し、県民に避難所等を提供しているほか、市町村が実施する防災ラジオの購入、防災行政無線を屋内で聞くための受信機の設置など、住民への情報伝達手段の整備に対して、県の南海トラフ地震等対策事業費補助金で支援している。
【富田昭雄委員】
県は指導する立場で、現場の市町村がしっかりと呼びかけを行う必要がある。自分自身も北海道で災害が発生し、避難した経験があるが、翌日には避難したホテルから出て行ってほしいと言われ、市役所から誘導された寝る場には食料も毛布もない状況だった。避難誘導の際のリーダーとなる人がしっかりと誘導できなければ、幾ら想定していてもそのとおりに進めることは難しい。
ただ単に、お金を出す、物を渡すだけでは済まないため、想定をしながら進めなければ、いざというときに機能しなくなると感じた。実際に市町村としっかりと議論して備えてもらいたい。
その上で、スフィア基準はどのような基準か。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
スフィア基準は、かつてアフリカのルワンダの難民キャンプで、劣悪な環境で多くの人が亡くなった反省から、国際赤十字、NGOなどを中心に立ち上げられたスフィアプロジェクトにより、災害や紛争の影響を受けた人々が、尊厳のある生活を営むために必要な最低の基準として、1997年に作られた。
スフィア基準は、元来難民キャンプの生活環境について示されたものだが、トイレの衛生、1人当たりの居住スペースなど、災害時の避難所に適用できる基準も一部含まれている。このうち、避難所における避難者1人当たりの居住スペースは最低3.5平方メートルとされている。トイレについては、発災初期の段階では50人に1基、さらに避難が長期化する段階では20人に1基のトイレが必要で、また女性用と男性用のトイレの割合は3対1とすることが示されている。
【富田昭雄委員】
基準は設けられているが、なかなかそのようにはいかない。実際、能登半島地震でも基準どおりになっていない。
市町村において、避難所のスペースを作る上で基準がマニュアルで決められていると思うが、段ボールベッドやテント、トイレを含め、購入してどこかに置いてあるのか。県が予算を出して購入しているのか。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
最近の大規模災害の反省を踏まえ、各市町村でも備蓄が進められている。また、県においても、物資を取り扱う事業者と災害協定を結んでおり、災害時にそれらの業者からの調達を計画することと併せて避難所の環境を確保していく。
【富田昭雄委員】
大事なトイレについてはどうか。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
トイレについて、市町村、県において備蓄している。また、それを補えるよう、協定事業者と協定を締結し、調達できる体制を整えている。併せて、大規模災害時には、国からのプッシュ型として被災地にトイレを供給するなどして必要なトイレ数を確保していく。
【富田昭雄委員】
南海トラフ地震等対策事業費補助金があるため、有効に活用してほしいと思うが、南海トラフ地震対策事業費補助金について、市町村とどのように話合いをしているか。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
南海トラフ地震等対策事業費補助金では、避難所に設置するトイレや段ボールベッド、パーテーションなどを市町村が調達し、活用できる。今年度も、トイレカーを含め、避難所で活用するそれらの物資を調達してもらい事業を進めているが、今後も財源を有効に活用してもらえるよう、機会を捉えて財源制度の説明会を行うなど、市町村の取組を支援していきたい。
【富田昭雄委員】
県がお金を出すだけではなく、市町村が十分に取り組めていない場合は、しっかりと議論、チェックし、指導する、人を派遣するなどして備えるとともに、民間の力を借りられるような体制を作ることが肝腎である。